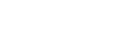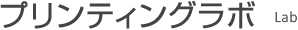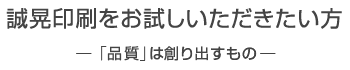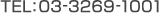オフセット印刷と静電気
冬などの乾燥時期においては、印刷加工では静電気による問題が発生しがちです。静電気はモノとモノを擦り合わせると発生するようなイメージがありますが、実際にはもっと様々な状態で発生します。印刷機なら、ブランケットから紙をはがすときはもちろん、インキの流れやローラーの摩擦、冷却水の流れなどからも発生するようです。様々に発生した静電気は、湿度が下がり、空気中の水分量が減ってくると、空気を通した放電が少なくなって用紙に帯電してしまいます。そうすると紙同士がくっついてしまい、印刷機にうまく紙が入らない、出てきた紙が揃わないという現象が生じます。
印刷工場内は加温加湿しておりますが、H-UV機はUVランプを使うため、UV光線とともに熱が発生します。この熱は、紙の内外の水分量を減らすことにつながり、放電が妨げられ、紙がさらに帯電することにつながるのです。
対策としては、「静電気の発生量を抑える」「静電気を放電させる」「静電気を吸収させる」のいずれかしかありません。静電気の発生量を抑えるためには、機械の回転数を落とすのが有効です。ゆっくり擦るほうが静電気は発生しづらいというのは、誰もが経験上わかっていることでしょう。
静電気を放電させるためには、水分量の確保しかありません。加湿して空気中や紙の中の最適な水分量を確保することができれば、水分を通じて放電が進んでいきます。
静電気を吸収させるために、電子を吸収する+イオンを発生させる手法があります。機械メーカーなどが静電気除去装置として設定していますが、実はエアコンなどで使われているイオン発生機(プラズ○クラスターなど)と原理は同じです。マイナスで帯電している電子をプラスイオンで相殺して消していくことができます。
このあたりは、出来上がった製品を見ている限りでは全くわからない話ですが、実は見えないところで印刷会社が苦労しているパターンはとても多いのです。こういったノウハウも、特殊印刷などと同じくらい重要です。
印刷業界ならでは →「ヤレって?ゴーストって? 印刷で出てくるおかしな言葉」